「急かさない復興」
またもや日付が空いてしまいました…。この日は報告をはじめた順番で言うと20番目になるみたいです。間が長らく欠番状態になっていますし、その前史(1月からの)も書くべきなのですが、あまり昔を振り返っていると忘れてしまうので、ここで時間軸を現在に戻して、できる限り簡潔に、報告していきたいと思います。なので急かさないでくださいね汗。
ということで28日は(もう第何次派遣か面倒で数えなくなりましたが)、ボラさんと合流して到着早々、ファイリングだの片付けだの。こちらにいてもパソコンやスマホと睨めっこで、こちらの現地のニーズと、大学が送り込んでくださる学生ボラさんとのマッチングに時間を取られる日々です。さすが連休、今回は最大で30名近い学生さんにお願いし、あちこちに送り込むことなるので、相当、緊張気味です…(自分はずっと門前ですが笑)。でうまく寝られず早起きして、科研費の報告書だの連休明けの授業準備だのをする始末。東京で能登のことを考え、能登で東京の仕事をする。完全に支援と日常が混ざり合っています。
でも、それではダメだと思ったのです。
それに気づかされたのは、4月28日「禅の里交流館」の駐車場でやってくださった、門前の「縁」さんの夜の屋台でした。本日、はじめてのチャレンジということで、早速、駒澤大学や学習院大学のボラさんたちと、大人買いしてしまって(経済支援、笑)、堪能してしまったのですが(炊き出しでなくお刺身なんて贅沢すぎ)、まだ片付いていないお宅ばかりの空間で、それでもゆっくり会話を楽しむ時間の中で、こういうコミュニケーションをとりあう時空こそが、求められているんじゃないか、と思うのです。
東京や東北の視点から能登を見ていたり、能登で東京や金沢からどう見られるかを意識していたり。
そんななかで、私たちは、「復興を急かせて(せかせて)」は、いないか?
それって、本当に、能登で生きている人、生きようとしている人が求めている、復興の姿なのか?
急いて生きてしまっている人間に、大地と海と歴史とゆっくり会話してきた能登が、本当にわかるのか?
わかったつもりになって語る。これが1番、自省しなければならないところです。
東北の「失敗・成功」、金沢の「創造」、東京の「ビジョン」…。どれも理想的なものなのだと思います。でもなんか大仰すぎて、「ここで生きること」から、ズレてしまいそうな気がするのです。そして、その「ズレ」こそが、被災地の過疎化・空洞化を加速しかねないのではないか。
なんでそう思うのか。ぼんやりとですが見えはじめてきました。私の本質は「書き手」なので、言葉にする努力をしていきたいと思います。被災地の共同的で自律的な復興のために。いよいよです。
活動報告 4月28日(日)
10:00 妙高出発。やっぱ高い…。
13:00 新高岡で学生と合流。初の駒大生!学習院もいてくれるよ。
15:00 七尾の百円ショップでサロン準備。七尾は日常化がすすむ。先月の羽咋みたい。
16:00 禅の里交流館でもうお一人と合流し準備開始。
17:00 今回の宿泊所(まだ未公開)の確認。なかなか…大事なことを考えさせられる。
18:00 お風呂は今日は男子がVネット。ボランティアがする範囲を超えていると感動します。でも、連休明けから自衛隊が完全撤退したら、はたしてどうなるのだろう。お風呂って、国が保障するべき最低限の文化的生活には入らないのだろうか…。
19:00 うわさの「縁」さんの夜屋台へ。ハビタットさんとご一緒。あんりさんこんばんは。堪能。本当は毎日、やってほしいぐらい。
20:00 就寝?できるわけがなく。師匠のダジャレが恋しい。
23:00 約束どおり、自分で消灯。これからどうなってしまうのでしょうか?


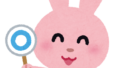

コメント